はじめに
夜中に突然始まる赤ちゃんの大泣き…。いわゆる「夜泣き」に、私も何度も悩まされてきました。仕事があるのに眠れない、妻が限界に近づいている、でも泣きやまない──パパにとっても大きな試練です。
この記事では、我が家の夜泣き体験と、パパとしてどう関わったか、試してきた工夫をまとめています。これから夜泣きと向き合うパパ・ママの参考になれば嬉しいです。
赤ちゃんが夜泣きをする理由
赤ちゃんが夜泣きをするのは成長の一部です。特に生後8か月〜1歳ごろは、急激な成長に伴って「唸り声」や「寝言泣き」が増える時期でもあります。原因はいくつもあります。
- 睡眠リズムの未発達: 浅い眠りのときに唸ったり、泣き声を出したりする。
- 空腹や喉の渇き: 特に授乳間隔がまだ安定していないときに起こりやすい。
- 体の不快感: おむつの濡れ、暑さ寒さ、服の違和感など。
- 精神的な不安: 親の姿が見えないと不安になって泣くことも。
つまり「夜泣き=親のせい」ではなく、発達の過程で自然に起きるものと考えるのが大切です。
我が家の夜泣き体験(パパ目線)
① 育休中の「夜勤担当パパ」
産まれてから1か月間の私の育休中は、夫婦で完全分業。私は夜勤担当として夜中の対応を引き受け、妻は朝早く起きて赤ちゃんの世話を担当しました。この役割分担のおかげで、お互いに最低限の休息を確保できました。
② 8か月〜1歳ごろの「唸り」対応
娘が8か月を過ぎると、急激な成長とともに夜中に「唸る」ことが増えました。泣き声とは違い、半分眠っている状態のような唸りです。この時期は本当に泣いているのか、眠りが浅いだけなのかを見極める力が必要でした。
我が家ではネントレを意識し、「鼻息や反応」で状態を観察。例えば、目を開けていても鼻息が寝ているときに近ければ半分寝ている証拠。そのまま抱っこせずに様子を見ると、自分で再入眠できることがありました。熟睡時には唇を軽く触っても反応しないなど、観察を通じてパターンを見つけました。
③ 泣いているときはすぐ抱き上げない
我が家では、夜泣きのときにすぐ抱き上げるのではなく、まずは5分〜10分様子を見ることを意識しました。なぜなら、泣いているからといって必ずしも抱っこや授乳が必要とは限らないからです。
実際、少し泣いたあとに再び自分で眠りに戻ることも多く、むしろすぐ抱き上げると完全に目が覚めてしまうこともありました。
④ 泣いて眠るメカニズムの理解
大人は眠るとき、副交感神経が優位になって自然と眠気が訪れます。しかし赤ちゃんはその切り替えがうまくできません。そのため、寝る直前に交感神経を強く働かせてギャン泣きし、それをスイッチに副交感神経へ切り替えるという独特の眠り方をします。
つまり、赤ちゃんにとって「泣くこと自体が入眠の儀式」なのです。だからこそ、無理に泣き止ませようとすると逆効果になり、かえって眠れなくなることもありました。我が家では「泣かせすぎない範囲で、一旦思いっきり泣かせる」ことを大事にしました。
⑤ 土日の「パパ当番」
平日は私が仕事だったので、夜泣きのメイン対応は妻が担当してくれていました。ただし、土日だけは私が寝床を交代し、妻をしっかり眠らせるようにしていました。部屋を分け、妻にはゆっくり休んでもらう。これで妻の体力と気持ちが少し回復し、平日も頑張れるようになりました。
⑥ 抱っこや添い寝で安心感を与える
泣き声が強まったときは抱っこや添い寝で対応しました。パパの体温や声でも十分安心してくれることを実感し、「自分でも役に立てている」と思える大事な時間でした。
専門家が勧める夜泣き対応
小児科医や育児書では、夜泣き対応について以下のようにアドバイスされています。
- 無理に泣き止ませようとしない: 泣きやませようと焦るほど、親子ともに疲れてしまう。
- 安全を確保する: 窒息や転落の危険がない状態で添い寝や抱っこを。
- 生活リズムを整える: 昼間にしっかり活動する、寝る前は明かりを落とすなど。
つまり「夜泣きはゼロにはできない」けれど「対応の仕方で少し楽になる」ことがポイントです。
まとめ
赤ちゃんの夜泣きは、パパにとっても試練のひとつ。我が家では「育休中は夜勤担当」「8か月以降は唸りを観察して再入眠をサポート」「泣いているときは5〜10分様子を見て、自律的な入眠を促す」「土日は寝床交代で妻を休ませる」などの工夫で乗り切ってきました。
泣き声や唸りに焦る夜もありますが、「夜泣きは成長の証」と考えると少し心が軽くなります。無理に完璧を目指さず、夫婦で協力しながらゆるく乗り切っていきましょう。
パパからのアドバイス:
夜泣きは夫婦で分業しないと共倒れになります。無理せず交代制にして、お互いの体力を守ることが大切です。
また、夜中は抱っこしすぎると完全に目が覚めてしまうこともあるので要注意。
その代わり、昼間はたっぷり抱っこして安心感を与えてあげてくださいね。
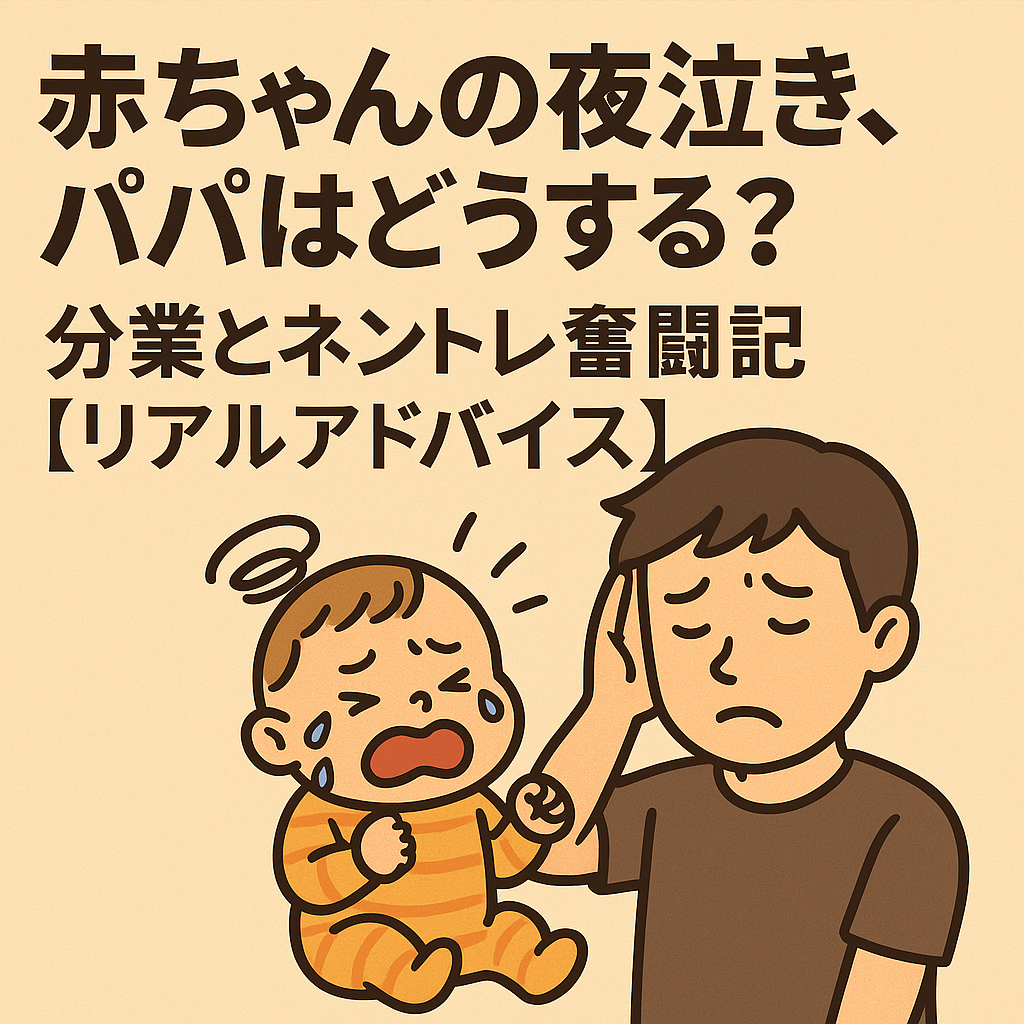








コメント